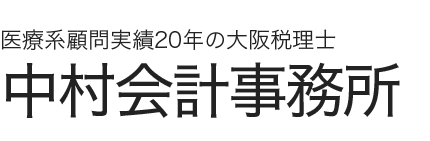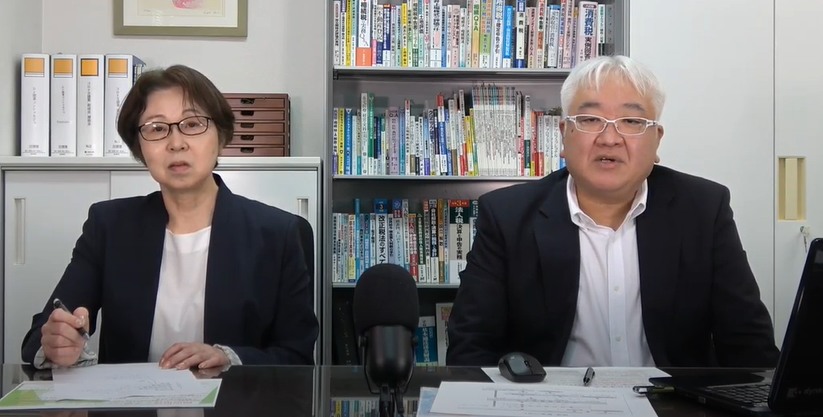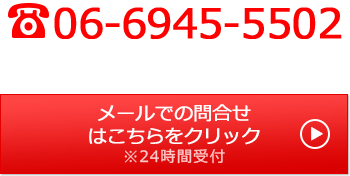事業所得と給与所得
事業所得か給与所得か判断の基準
もし、給与所得と事業所得を納税者の任意に区分する事ができるとすれば 「何故 所得の区分が重要になるか?」 のページでご覧いただけるように同じ収入、同じ支出経費があったとしても納める税金に差が出てしまいます。役務の提供により高額収入を得られるドクターや弁護士さんの場合は、税務署側が所得の区分にこだわるケースが多いように思われます。一時期まだ景気のいい時代には、サラリーマン向けに「誰でも彼でも雇用契約を外注契約に変更して事業所得者となった方が得です。」的な指南書が出ていましたが、所得の区分について税務署がこだわらなかったのは、そんな事をしてもさほどのメリットが見込めない(若しくは、むしろ給与所得にしておいた方が税金は安かった)からだったのではないでしょうか?
給与所得と事業所得を納税者の任意に解釈できるとなると、対価を受け取る側はその額を調整して税金を安くする事が可能になってしまいますし、雇用者(発注者)側は、労働基準法に縛られず、いつでも役務の提供者を切り離す事が出来、又支払った費用は給料なら出来ない消費税の仕入税額控除の対象となる等、支払額を外注費用とする事で受取側と支払側の利害関係が一致するケースも考えられます。
税務署側も勤務先(外注元?)から出てくる調書(給与所得の源泉徴収票か報酬の法定調書)だけでの表面的な判断にだけでなく下記のような基準を基に所得の区分を判断しています。
1.その勤務先での地位は労働基準法の適用を受ける要件となっているか?報酬の支払い基準に各種手当が含まれているか?
有給休暇があったり、報酬に通勤手当が含まれていたりするとご本人も勤務先も給与所得者との認識があるように思われます。
2.仕事の依頼者はその仕事について指揮監督をしているか?
役務提供の場所を指定したり、タイムカード等で時間の管理をしていれば雇用契約という判断に傾きそうです。
3.仕事の成果物が不可抗力の為滅失した場合にもその報酬を請求できるか?
給与所得者なら、余程故意に近い不注意が原因で会社に損害を与えなければ、給料を減らされる事も賠償を求められる事もありません。
4.役務の提供にかかる材料又は用具を会社が提供しているか?
会社は、通常会社の業務に必要な材料か消耗品は従業員の為に用意するものです。
以上のような点を基準に、他にも細かい個々の状況を元に、所得の区分の判断がなされるのは、裁判でも税務調査でも同じです。